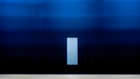ドローイングダンス
失われた線を求めて

構成. 振付. 演出. 美術. 照明. 衣装. 作曲 勅使川原三郎
アーティスティック コラボレーター 佐東利穂子
出演 勅使川原三郎、佐東利穂子
ドローイング 勅使川原三郎
舞台監督:立川好治、金子芳浩(ニケ ステージワークス)
照明技術:清水裕樹(ハロ)
音響技術:三森哲弘(エスアールテックプランニング)
ドローイング撮影 阿部章仁
協力:加藤智子、宇佐美雅司
主催:有限会社カラス
企画制作:KARAS
特別提携:シアターX(カイ)
助成:文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術活動活性化事業)
独立行政法人 日本芸術文化振興会
上演時間:60分
初演:2022年10月 両国・シアターX
アーティスティック コラボレーター 佐東利穂子
出演 勅使川原三郎、佐東利穂子
ドローイング 勅使川原三郎
舞台監督:立川好治、金子芳浩(ニケ ステージワークス)
照明技術:清水裕樹(ハロ)
音響技術:三森哲弘(エスアールテックプランニング)
ドローイング撮影 阿部章仁
協力:加藤智子、宇佐美雅司
主催:有限会社カラス
企画制作:KARAS
特別提携:シアターX(カイ)
助成:文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術活動活性化事業)
独立行政法人 日本芸術文化振興会
上演時間:60分
初演:2022年10月 両国・シアターX
私のドローイングとダンスの関係がどのようなものかを
いくら考えてもはっきりと言うことができない。
紙の上に線を描く自分の手は踊る自分の身体と同じものなのか?
いや線が身体なのか?描くペンが身体なのか?描かれた線の動きは
身体の動きなのか?ドローイングの線は残され、身体の動きは消えてゆく。
描く手は残り、身体は動きながら消えてゆく。
再び現れては消えるべく動きを起こしては幾度も消えてゆく。
ドローイングはいつまでも起ころうとするが消しゴムで消され、擦られ薄められ厚みを変えられる。
あくまでも線は受け身である。身体がいつも受け身であるように自らが立つことができない。
立たせられている。その受け身を負っているからこそ、動かされる、いやまるで自らが動いている
ように見えはする。そうすると線が自ら動いているのではないようだし、
身体は動かされているのだとすれば、
線と身体の動きがほとんど同一次元に運動しているように感じられてくる。
手に握られているペンの先から鉛筆の芯の擦れ痕としての線の延長が重層し構成する面を
ドローイングというなら身体の動きによって重層による重奏を構成する面をダンスといえば、
その互いの区別が無くなりいずれも身体の運動によって露わにされる内的衝動の表出であり、
直感の直接と間接とが時間差を伴いながら営まれる自己に対する共感と裏切りへの賛美する形と
言えなくもない。
ここに表されるものは、実質的に無価値に等しい、まるで意味の無い身体運動なのである。
そして、こうしているうちに私が思うのは、私にとってドローイングとダンスの関係は
ほとんど分からないままに放置されている、ということのみである。
稽古場の片隅に転がる身体であり、机の上に放り出されたペンである。
なにかが起こる予兆など皆無なほど無力な静かな影である。
しかしそれらを見る者として私が密かな衝動をできる限り潜めているのも実際である。
密やかな衝動と平衡する生命運動は、私のある種の緻密さによって的確に表出され、消滅され、
沈黙の歓喜の中で乱舞するのである。
震える微細な動きの交わり、
身体と線の交わり、
表面の裏側に光、
光の後ろの笑顔。
勅使川原三郎
ギャラリー
レビュー(抜粋)
素描という起点 水沢 勉氏 美術評論家、神奈川近代美術館 館長
いまから30年以上の時を遡る。その頃の勅使川原三郎の存在感を際だたせた出版物として『青い隕石』(求龍堂、1989年)が知られている。同書をはじめて手にしたとき、モノクロームのドローイングが複数紹介されていて心底驚かされた(pp.28-34)。そして出版記念パーティ会場にはそのオリジナルが並んでいた。素描家としての才能のきらめきを直に確かめることができた。
美術に関心の深かった勅使川原三郎にとって素描は早くから身についていた表現方法のひとつであったはずだ。当時、ダンサーとしてのデビューの衝撃波が残っていたこともあって、同書掲載の詩的断片群の喚起力と相俟ってなんと豊かな才能の持主であるかとしばしオリジナルを前に息を呑んだ。
しかし、その後、勅使川原三郎の表現者としての歩みを辿っていくと、画家としての側面は付加されたエピソード的なものではなく、その本質に深くかかわっていることがはっきりした。多才の一端、ではなく、むしろ、その核心ではないかと思えてきたのだ。
その創作の熱量は下がる気配がまったくない。荻窪にある「カラス アパラタス」の壁面には、無数の素描が途切れることなく発表され続けている。
ドローイングは素(す)の状態の描画である。まさに引く(draw)線を主体とする素画。
そこに表現者・勅使川原三郎のすべてが起点として宿っている。それは舞台面の光の効果に結びつくと同時に、その構成も暗示する。さらにはそこに展開する物語をも超現実主義的空間に孕むこともある。そして、それを描く指と手と腕などの身体と頭脳とが閃光のように直結する。つまり素画は、身体表現=ダンスのエッセンスというべき素型なのだ。
美術に関心の深かった勅使川原三郎にとって素描は早くから身についていた表現方法のひとつであったはずだ。当時、ダンサーとしてのデビューの衝撃波が残っていたこともあって、同書掲載の詩的断片群の喚起力と相俟ってなんと豊かな才能の持主であるかとしばしオリジナルを前に息を呑んだ。
しかし、その後、勅使川原三郎の表現者としての歩みを辿っていくと、画家としての側面は付加されたエピソード的なものではなく、その本質に深くかかわっていることがはっきりした。多才の一端、ではなく、むしろ、その核心ではないかと思えてきたのだ。
その創作の熱量は下がる気配がまったくない。荻窪にある「カラス アパラタス」の壁面には、無数の素描が途切れることなく発表され続けている。
ドローイングは素(す)の状態の描画である。まさに引く(draw)線を主体とする素画。
そこに表現者・勅使川原三郎のすべてが起点として宿っている。それは舞台面の光の効果に結びつくと同時に、その構成も暗示する。さらにはそこに展開する物語をも超現実主義的空間に孕むこともある。そして、それを描く指と手と腕などの身体と頭脳とが閃光のように直結する。つまり素画は、身体表現=ダンスのエッセンスというべき素型なのだ。